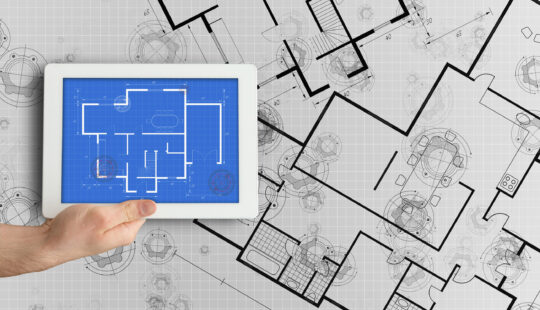
建設業から見たERP
建設業では、労働人口が減少する中、熟練技能者の技・ノウハウ・勘の伝承や、働き方改革の潮流により現場生産性向上の課題に直面し、業務品質の維持・改善が問われている。そのため、今まで以上にICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の積極的な活用に取り組み始めている。
ここ数年の我々への引き合いの数を見ても確実に増加傾向にあり、”経営管理情報の可視化”や”業務効率改善”などが取り組みテーマとしてあがっている。これらの検討では、総論として ”ワンファクト・ワンプレイス”や”全体最適”、”業務標準化”などの(ERPの)コンセプトが含まれている。その一方で、海外建設業の適用例と比較すると、「現場」までへのコンセプト適用に大きな障壁があることは明らかだった。
そんな時、北米で事業展開する建設業のコメントが目に留まった。
”Making Work Faster and More Efficient from the Construction Site to the Back Office”
現場からバックオフィスまでの作業をより速くより効率的にする
このコメントの通り、建設業の多くは、現場とそれを管理する支社機能、それらを束ねる本社機能の3階層で構成されている。そのため、現場のインプットが支社、本社にリアルタイムで反映できれば、組織間に存在する間接業務は削減できるだけでなく、作業をより速くより効率的できるはずなのだ。
残念ながら、なかなか実現にまで至っていない状況があり、そのギャップを探る必要を感じていた所に、幸運にも、現場プロセスへのERP適用を評価できる機会を得ることができた。上記コンセプトに意見を求めると、やはり同意は得られた。ただ、それだけでは現場に共感を得られないという。その理由を尋ねると、もっともな意見があった。
- 大半の効果は支社/本社側であり、現場側が動く理由になりづらい
- プロセス効率の話を進めても、クライアント/協力パートナー側のデジタル化の遅れがネックになり、その先が進まない
- 現場の責任で動かす以上、自分達のやり方でやりたい
- 結果、各現場が個別に最適化し続けられれば、全体最適と変わらない
だからと言って、決して現在のサイロ構造が良いと言っている訳ではない。誰もがこのような状況は何とかしたいと思いながらも、現場が納得できる理由が見つけられずに、今の構造を変えられないでいるのだ。
そんな時に、冒頭のコメントをしていたグラハムグループ(以下、グラハム)のケースに出会った。そこには、10年以上ERPを使い続ける彼らが、段階的に進化している姿が描かれていた。
グラハムの特徴
グラハムは、カルガリーに本社を置き北米全土に事業を展開する建設会社で、「北米No1の建設ソリューションパートナーになること」を目標に掲げている。1926年に駅の建設から始めた事業は、専門知識を広げ、様々なタイプの建物や産業インフラ、公共施設、P3事業に至るまで様々なカテゴリーに事業を展開している。また、彼らはメインコントラクターだけでなく、サブコントラクターや協力パートナーなど、状況やニーズに応じて役割を変化させている。100年近い歴史を持つ企業であるとはいえ、これだけの多様な事業を展開できるのは大きな特徴だろう。それは、専門知識や経験を取得するには時間が掛かる上、専門性を売りにする競合企業とも差別化できなければならないからだ。
”We continue to be at the leading edge of both software technology and sustainable construction practices”
ソフトウェア技術と建設プラクティスの両方で最先端企業であり続ける
この発言のように、彼らの特徴を下支えしているのは6つのサクセスドライバーから構成される「IT戦略」といっていいだろう。
- Construction Expertise
- Integrated Capabilities
- Self-Perform Capabilities
- Financial Strength
- Technology Innovation
- Learning & Development
ここからは、グラハム社の取り組みを紐解きながら、現場プロセスにERPを適用する理由を探ってみることにする。
今できていないことにアドレスして価値を示す
専門知識や経験も重要ではあるが、プロジェクト遂行を支える能力しかなく、結局の所、現場では良質な建設物を予算以内、かつ工期を遵守し、作業の安全と環境に配慮できることが重要となる。つまり、Quality(品質)、Cost(原価)、Delivery(工期)、Safety(安全)、Environment(環境)(以下、QCDSEと表現)を管理できる能力が求められる。
一般的にこれらは、2種類のデータを管理する必要がある。原価や工期を代表される「業務データ」と、品質、安全、環境などに代表される「ドキュメントデータ」なのだが、これらデータが個別に管理されている。これらの情報が同じタイミングで、関係するステークホルダーに共有されれば、間接付帯業務が最小化できるだけでなく、業務プラクティスの再利用など現場での生産性向上に大きく貢献できる。この理屈は通用しても、まがりなりにも今もできていること以上のベネフィットを享受できない以上、「今を変える理由にはならない」のである。
その一方で、グラハム社の文脈はこうだ。
実際の建設プロジェクトは立地や気候など様々な条件により変更が発生する。当然、スケジュールの見直しが入れば、資材や人材の投入のタイミングも変わり、原価にも影響を与えるかも知れない。また、品質に影響を及ぼす事象が発生すれば、設計の見直しのケースすらある。このように、ひとつの変更が複数の組織やプロセスに影響するため、彼らは業務プロセスの統合にこだわり、それらを全社(現場/支社/本社)でサポートするため業務基盤を整備していた。
単に組織横断で情報を収集・加工するだけであれば、業務プロセスを統合する以外の解決策も考えられる。しかしながら、彼らはプロジェクトの管理能力を向上させるために、現場以外にも専門性を持たせ組織横断で現場をサポートできる体制を構築している。その一例に、「プロジェクトリスクの評価・管理業務」があった。しかも、彼らは(その専門知識を用いた)管理サービスを、グループ内に留まらず、顧客や協力パートナーにも提供している。このように、社内の管理プロセスを成熟させ、そのプラクティスをステークホルダーに還元しているのだ。自分たちのノウハウや経験の使い道は、社内の生産性向上に留まりがちだが、このモデルは新たなサービスとして提供できる可能性を示唆してくれている好例である。
自分達のやりたい世界を明確に描き共感を得る
ビジネス自体、協力パートナーへの依存度が高い建設業では、自分たちのパートナー・エコシステム開発は重要なテーマとなる。ただ、その企業規模はさまざまで、公共事業などでは地域パートナーとの連携も必要となる。このように、幅広いパートナーとのエコシステム開発が求められる一方で、規模が異なれば当然ITリテラシーも異なるため、手間の割には効果が見えにくく、積極的にIT投資ができなかった領域のひとつかもしれない。
グラハム社も例外なく同様の問題を抱えていた。彼らは「協力パートナーも重要なステークホルダーである」という価値観を持ち、「彼らに変わってもらうために何をすべきか?」を前提にIT施策を進めていた。
前段で触れた統合システムは、見積からプロジェクト管理、調達、生産などプロジェクトフェーズを通じ、必要な関係者に必要な情報がリアルタイムで提供される仕組みであり、プロジェクトを通じて関係するステークホルダーは、社内外を問わずコラボレーション基盤として利用できる。つまり、“現場からバックオフィスまでの作業をより速くより効率的にする”という彼らのビジョンは、社外のステークホルダーも協働利用できることが前提になっていたのだ。
また、この前提はパートナー採用・開発にも色濃く反映されており、正式採用された協力パートナーには、専用ポータルを通じてグラハム社の持つベストプラクティスやガイダンスなどを学習する機会も提供されていた。このように、グラハム社は自分たちが描く世界観にパートナーも積極的に参加させることで、デジタルを利用するハードルを下げている。かつては、紙ベースで運用していた協力パートナーの工数管理なども、現場の声を反映しながら、支払プロセスなどのバックオフィス業務も含めオンライン化され、現場だけでなくその管理業務の省力化も図っていた。
彼らにして見れば、「自分達が実現したい成功基準を明確に描き、それに共感してもらった仲間には支援をする。さらに、その取り組みを改善して進化させていく」ことは当たり前のことなのだろう。協力パートナーのデジタル化をただ待っていても改善される訳ではない。自分達のやりたい世界に共感を得られたパートナーとは、一緒にやり方を考えながら前に進めてみるべきかも知れない。
検討アプローチの再考を促す
“革新的な情報技術を早期に採用し、仕組みを進化させ続ける”
これは、グラハム社のITビジョンである。自分達が何を革新的な技術と捉え、どこまで進捗したのかを振り返り、ホームページ上で公開している。このアウトプットが良いかは別として、自分達が辿りついた点を明確にすることで、その先にどのような進化できる世界があるのかを示し、ステークホルダーを積極的にインフルエンスしていく姿勢は素晴らしい。
Source : Construction Then & Now: 2000 vs 2020:Grahamを著者が妙翻
このように、デジタル能力を使って、皆に「何ができそうか?」を想像させたり、アイディアを考えたりと、検討アプローチを工夫することでワクワク感を醸成することは、ステークホルダーを巻き込む上では非常に重要ではないだろうか。
まとめ
グラハム社は、ICTを積極的に活用した差別化戦略を描き、実行している企業だった。加えて、ひとつひとつの取り組み内容は、基本に忠実あり、この変革に近道がないことも再認識させてくれた。
その中でも、ステークホルダーから共感を得るのが抜群にうまかった。
人を動かすことに長けている建設業だからなのかはわからないが、彼らは“相手に興味を持ってもらい、相手を観察しながらアプローチを考え、そして実行して修正していく“というこの当たり前のことを着実に繰り返していた。多くの他業界で採用されている、現場にも共感を得て進めるアプローチが、建設業でも有効であることを証明してくれた。
コミュニケーションひとつとっても、現場から見たペインポイントに対し、ERPが有効な手段であること丁寧に実行していた。当たり前の話だが、共感を得たい相手(現場)を主語にしたコミュニケーションを徹底していた。つまり、手段(ERPなど)を主語となるコミュニケーションはタブーなのである。
また、動かない相手に対しても、「自分たちのありたい姿」を示しながら、相手の文脈を紐解きながら共感を得ていった。その際には、ステークホルダーに対して、自分たちが対話する相手として認められる努力を日頃からやっておく必要がありそうだ。
※本稿は公開情報をもとに筆者が構成したものであり、Graham Group社のレビューを受けたものではありません。
